今回紹介する本は
「ギフテッドの光と影 知能が高すぎて生きづらい人たち」
です。
どんな内容の本なの?

「同級生と話が合わない。なじめたことは一度もない。授業はクソつまらない」
HonyaClub より
……IQ130以上がひとつの基準ともされるギフテッド。
強い個性ゆえに周囲になじめない現実を描く。
朝日新聞の人気連載「ギフテッド 才能の光と影」を加筆。
そもそも「ギフテッド」ってなんだろう?

ギフテッドは、平均より著しく高い知的能力を指す用語。
学校への入学許可の決定や個人の生涯を通じた長期的研究の多くは、
上位2.5パーセントの知能指数(つまりIQ130以上)を持つ人々を対象としている。ギフテッドの定義は多様であり、
Wikipediaより
総合的な高い能力を基準とするものもあれば、
特定の分野で発揮される高い能力を基準とするものもある。
第1章 とびぬけた頭脳、なじめない環境

5人の例が取り上げられていますが
彼ら彼女らの共通は「IQが高い」がゆえに
各々の生活で「生きにくい」ことがあげられています。
・IQ154、小4で英検準1級の少年
・36歳で知った、IQと私の居場所
・「5度の視野」から鳥を見る、特別な目の少年
・「できる自分」を隠したIQ140のろう者
・能力を発揮するたび上司と衝突、広がった「ずれ」
第2章 「ギフテッド」とはどのような人か

ギフテッドはどのようなことか
IQが高いということは、日常生活においてどのような弊害がおきるのだろうか
第3章 特異な才能の受け皿
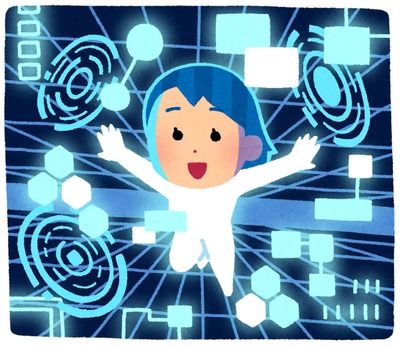
天才たちの才能をもっと引き延ばしたいという、孫正義の財団
ギフテッドの特性ある子供たちの居場所にしたいというNPOのメタバース空間
いち早く「ギフテッドクラス」を作った学園の挑戦と挫折
ギフテッドの子どもたちのために動いてる大人たちの例です。
第4章 「才能教育」の過去と現在

実は戦時中の日本でエリート養成を行っていたという
当時それに参加した当事者のインタビュー、
また近年に東大プロジェクトとして行われた
「異才発掘プロジェクトrocket」、
各国のギフテッド教育についてまとめられています。
第5章 変わる日本の教育現場

現在の日本の教育方針と、
特異な才能をある子どもへのサポート案(提言)などが書かれています。
読んでみて

子どもの才能を伸ばすということはいったいどういうことなのだろう?
子どもの幸せとはなんだろう?
そう思わずにいられませんでした。
IQが高いがゆえに、学校の授業がつまらない
ひとりでもできる勉強は多いですが、
複数で学ぶことで得られることも多いとは思います。
ですが、この本に出てくる子どもたちはそういう次元ではなく
私たち大人が思っている枠以上に大人の知能を持っています。
年齢は身体は子どもだけれど、なんでも知っていて
「もっと知りたい!学びたい」
「でも学校は…」
となった時にいったいどうすればいいのか。
残念ながらこの本に明確な対処方法は書かれていません。
「学校になじめない」というキーワードで医療機関に相談し
そこで調べるうちにIQが高いと判明というケースが多いようです。
健常者だけでなく、障がいのあるかたのケースや
視野角が異常に狭いケースなどもあり
さまざまなケースがあることがわかります。
子どもだけでなく大人のケースも書かれていますが、
当時の彼ら彼女らは今以上周囲の理解を得られることがむつかしかったようで
それは社会に出た今も同じようです。
本書に書かれてはいませんでしたが
知識は大人以上でも、
心と身体は未成熟な状態であるので
思春期にはまた別の生きにくさが生じるであろうと予想できます。
(本書に中高生の事例はありませんでした)
大人である私たちに対して様々な働き方があるように
子どもにとってもさまざまな学び方が選択肢があってもいいと思いました。
知識欲だけでなく、心も身体も大人になっていくことができる
そんな支援が必要ではないでしょうか。
★Kindle Unlimitedなら
500万冊の人気のマンガ、雑誌も電子書籍が読み放題。
・人気のマンガ、雑誌も豊富。
・Kindleアプリで、いつでも、どのデバイスでも、読書をお楽しみいただけます。

【本日のサムネイル】
天才のイラスト(女の子)
黒板の上に難しい数式や図を書いている、天才少女(ギフテッド)のイラストです。




コメント